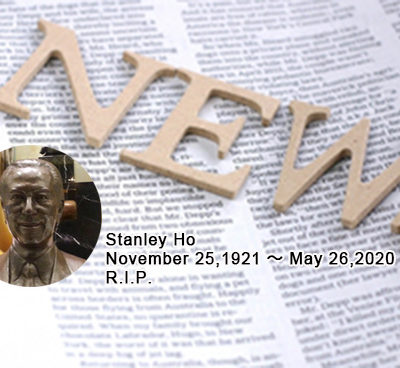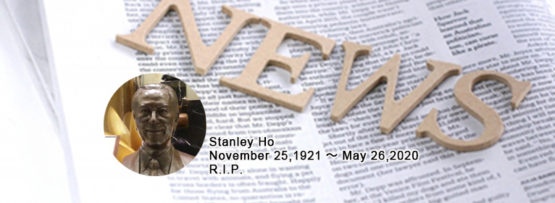マカオが再び脚光を浴び始めたのは、1684年に中国人による対日貿易が正式に解禁されたことを契機とする。厦門・広州・寧波・上海に海関を設置し、出海する中国人海商や来航する外国商船から関税の徴収を行うようになると、清朝の海洋貿易は活気づいていく。
とりわけマカオは、ヨーロッパ商人にとって重要な情報の集積地であり、欧州の風土が漂う独自の文化を形成していたため西洋の商人たちの国際的公共財という側面を作り上げていった。かつてのアジアの中の小さなリスボンは、アジアの中の小さなヨーロッパとしての輝度を増していくことになる。
このように数多くの貿易会社・貿易商人が集うマカオの中に、アジア各地の植民地経営や交易に従事する「イギリス東インド会社」があった。英中自由貿易を確立したいイギリスは、現行の広東地方一帯でのみ許させる交易に不満を抱いており、清朝との関係は緊迫したものになっていく。アヘンを利用した密貿易の拡大、アヘン取引に使用する銀の国外流出の阻止が顕著になると関係はさらに悪化し、アヘン貿易の全面禁止、そして1840年のアヘン戦争勃発へと時代は下っていく。このときマカオ(ポルトガル)は中立を維持して、清朝、イギリスどちらにも加担しない選択を選ぶのだが、これが大きな転換となるとは夢にも思っていなかっただろう。
2年後、清朝が敗北を認めると、南京条約でマカオから海を隔てて東へ約50キロの距離にあった香港島はイギリスに永久割譲されることが決まり、さらには広州、厦門、寧波、福州、上海の5港が自由貿易港となることで、マカオの特別的な地位は失われてしまうのだ。
19世紀、すでにポルトガルの海洋政策は過去の栄光となり、近代化著しい真の列強・イギリスに対抗できる術は持っていなかった。そのため貿易の中心は、イギリス領である香港と5港に移行していくのは自然の流れであった。 香港のヴィクトリア・ハーバーは水深に余裕があったため、珠江の土砂が大量に堆積するマカオの港湾に比べ砂や泥が積もりづらく、干満の潮位差も小さかった。天然の良港・香港へ、次々と多くの貿易会社が拠点を移していく姿をマカオはただただ眺めるほかなかった。歴史の表舞台に香港が登場したとき、マカオは二度目の危機を迎えるのである。