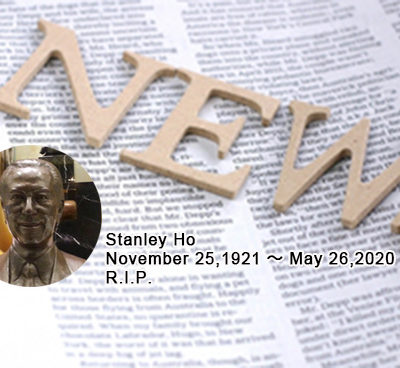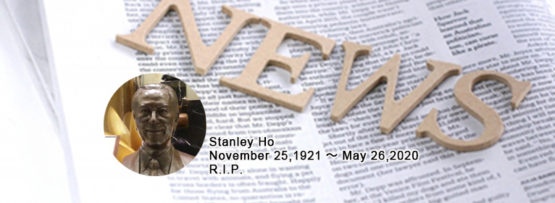当然、日本軍もマカオを利用し物資を調達していた。このとき日本軍への物資供給を取り扱っていたのが、後に「マカオのカジノ王」と呼ばれる若き日のスタンレー・ホー氏だった。マカオ近代化の父・ホーの人となりは別ページに譲るが、ホーが働いていた聯昌公司は軍資金の3分の1を日本人が出資していたとも言われている。
第二次世界大戦が終わると中国はマカオ回収に動き出す、はずだった。ところが、共に戦争を戦った共産党と国民党は日本軍という共通の敵がいなくなると、再び反目し合うようになり内戦に発展。国民党を破った共産党は1949年北京にて中華人民共和国を建国する。さらに、1950年に中国共産党政府を承認したイギリスとは対照的に、ポルトガルは反共産主義者であったアントニオ・サラザール首相による独裁政権下にあったため、中華人民共和国との国交を持たないという判断を下すことになる。
だが、中国は老獪であった。米ソ冷戦構造が長引くことを視野に入れた際、香港とマカオの返還を急がず現状維持することは西側諸国との窓口として重宝することが分かっていた。両地域を外貨獲得、華僑送金の主要ルートとして活かそうという中国の現実的な対応は、本来であれば負の遺産になりかねない植民地を正に転換させた逆転ホームランと言えるだろう。ベルリンに壁を築いたソ連のように資本主義と社会主義を断絶する選択を取らずに共存、しいては一つの国にあって異なる対応を採択した中国の合理性は、我々社会に生きる者として見習うものは大きいはずだ。
1955年、マカオはポルトガルの海外州に格上げされ、マカオで生まれたものは民族問わず、ポルトガル国籍を有することができるようになった。一方で戦時下に好景気に沸いたマカオが終戦後にその力点を失い、徐々に景気が後退していくことは明白だった。不安が増していく中で、1966年に中国全土でプロレタリア文化大革命が起こると、ナショナリズムに喚起されたマカオ在住華人の対ポルトガル感情は大きく悪化し、両国は緊張状態に突入していく。
そしてついに暴徒と化した住人と、鎮圧しようとしたポルトガル軍警察がぶつかり、警察の発砲により死者を出す「一二・三事件」が発生してしまう。この事件によって、マカオにおけるポルトガルの権威は完全に失われ、両国はこれからのマカオについてテーブルへつかざるを得なくなった。
以後、マカオ内政はポルトガル本国ではなく中国共産党の影響力が増し、スタンレー・ホーの盟友であり、「マカオの影の総督」と呼ばれた何賢を中心とした中華総商会が実権を握っていくようになる。